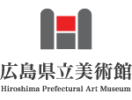所蔵品
所蔵品
天山南路(昼)
【作品解説】
うつむきながらも、ひたすらに歩む僧侶たち。天竺(インド)で求法(仏の教えや悟りの道を求めること)を終えて中国へと帰る僧侶たちの敬虔な姿を象徴的に描いた作品である。
タイトルにある天山南路は、中国新疆ウイグル自治区からキルギスタンにかけて走る天山山脈を通る行路。仏典を得るため、国禁を犯し天竺へ危険な旅を続けた玄奘三蔵のように、多くの求法僧が通った道であった。
平山は、険しい旅路の中で道に迷い、病に倒れ、あるいは盗賊に襲われて目的を達成できなかった僧侶にも思いを馳せ、この作品を描いた。
【作家略歴】
1930(昭和5) 広島県豊田郡瀬戸田町(現尾道市)に生まれる
1945(昭和20) 学徒勤労動員中の広島陸軍兵器支廠で被爆
1947(昭和22) 東京美術学校(現東京芸術大学)に入学
1952(昭和27) 同校を卒業後、新制となった東京芸術大学副手に就任。前田青邨に師事
1953(昭和28) 第38回院展《家路》ではじめて入選
1959(昭和34) 被爆の後遺症に悩まされる中、第44回院展《仏教伝来》で入選
1962(昭和37) 第47回院展《受胎霊夢》《出現》で受賞。東西宗教美術の比較のために渡欧
1966(昭和41) 東京芸術大学第1次オリエント調査団に参加
1968(昭和43) はじめてアフガニスタンから中央アジアに至るシルクロードを取材
1973(昭和48) 東京芸術大学教授に就任
1989(平成元) 同大学長に就任
1998(平成10) 画業50年展を開催。文化勲章を受章
2000(平成12) 奈良、薬師寺玄奘三蔵院伽藍「大唐西域壁画」を完成
2001(平成13) アフガニスタン、バーミアン大仏の破壊について抗議声明を発表
2009(平成21) 東京都中央区の病院にて没
うつむきながらも、ひたすらに歩む僧侶たち。天竺(インド)で求法(仏の教えや悟りの道を求めること)を終えて中国へと帰る僧侶たちの敬虔な姿を象徴的に描いた作品である。
タイトルにある天山南路は、中国新疆ウイグル自治区からキルギスタンにかけて走る天山山脈を通る行路。仏典を得るため、国禁を犯し天竺へ危険な旅を続けた玄奘三蔵のように、多くの求法僧が通った道であった。
平山は、険しい旅路の中で道に迷い、病に倒れ、あるいは盗賊に襲われて目的を達成できなかった僧侶にも思いを馳せ、この作品を描いた。
【作家略歴】
1930(昭和5) 広島県豊田郡瀬戸田町(現尾道市)に生まれる
1945(昭和20) 学徒勤労動員中の広島陸軍兵器支廠で被爆
1947(昭和22) 東京美術学校(現東京芸術大学)に入学
1952(昭和27) 同校を卒業後、新制となった東京芸術大学副手に就任。前田青邨に師事
1953(昭和28) 第38回院展《家路》ではじめて入選
1959(昭和34) 被爆の後遺症に悩まされる中、第44回院展《仏教伝来》で入選
1962(昭和37) 第47回院展《受胎霊夢》《出現》で受賞。東西宗教美術の比較のために渡欧
1966(昭和41) 東京芸術大学第1次オリエント調査団に参加
1968(昭和43) はじめてアフガニスタンから中央アジアに至るシルクロードを取材
1973(昭和48) 東京芸術大学教授に就任
1989(平成元) 同大学長に就任
1998(平成10) 画業50年展を開催。文化勲章を受章
2000(平成12) 奈良、薬師寺玄奘三蔵院伽藍「大唐西域壁画」を完成
2001(平成13) アフガニスタン、バーミアン大仏の破壊について抗議声明を発表
2009(平成21) 東京都中央区の病院にて没
| 名称 | 天山南路(昼) てんざんなんろ(ひる) |
|---|---|
| 作者名 | 平山郁夫 ヒラヤマ・イクオ |
| 時代 | 昭和35年 |
| 材質 | 紙本彩色 |
| サイズ | 164.2×218.8 |
| 員数 | |
| その他の情報 | |
| 指定区分 | |
| 分野 |